2021年4月、5月、6月分の日記です。
2021年4月3日 土曜日

麻生幾(あそう いく)さんの小説「救急患者X」を読みました。大学病院の救急救命センターが舞台の医療サスペンスホラーです。
ある夜、大学病院で起こった女性の飛び降りから物語は始まります。救急救命センターでは救命処置を施して、集中治療室(ICU)に入室した患者が身元不明の場合、この病院では「X」と呼称しました。飛び降りで骨盤骨折による腹腔内出血の患者X13、病院のトイレで倒れ外傷性くも膜下出血の患者X12、交通事故で全身熱傷と肝臓断裂のX14。二日間の間に、この3人の”外傷による”女性患者たちに起こる常識では考えられない不可解な出来事。3人がそろって口にした「救ってあげて!」という言葉。女子トイレの鏡に浮かび上がる「呪、恨、殺」の文字。生臭く湿った恐怖感の中で3人の関係性が浮かび上がる時、物語は意外な結末へと進んでいきます。
本作は、救急医療現場のリアルな描写が光だとすれば、そこで起こる科学とは矛盾する出来事が闇で、そのコントラストが恐怖感を高め、そこに謎解きの要素が加わることで作品の幅が広がったと思います。
麻生さんの作品は「宣戦布告」のリアルなディティールが好みだったので、本作はどうかと思いましたが期待通りでした。ただ、ネタバレになってしまいますが、連続レイプ殺人犯の山田が、自身の犯罪隠ぺい工作を、被害者の母親や友人が暴く行動をとることを知ることができたのはなぜか描かれておらず、物語のキモになる部分だけに、ちょっとモヤモヤ感が残りました。
ある夜、大学病院で起こった女性の飛び降りから物語は始まります。救急救命センターでは救命処置を施して、集中治療室(ICU)に入室した患者が身元不明の場合、この病院では「X」と呼称しました。飛び降りで骨盤骨折による腹腔内出血の患者X13、病院のトイレで倒れ外傷性くも膜下出血の患者X12、交通事故で全身熱傷と肝臓断裂のX14。二日間の間に、この3人の”外傷による”女性患者たちに起こる常識では考えられない不可解な出来事。3人がそろって口にした「救ってあげて!」という言葉。女子トイレの鏡に浮かび上がる「呪、恨、殺」の文字。生臭く湿った恐怖感の中で3人の関係性が浮かび上がる時、物語は意外な結末へと進んでいきます。
本作は、救急医療現場のリアルな描写が光だとすれば、そこで起こる科学とは矛盾する出来事が闇で、そのコントラストが恐怖感を高め、そこに謎解きの要素が加わることで作品の幅が広がったと思います。
麻生さんの作品は「宣戦布告」のリアルなディティールが好みだったので、本作はどうかと思いましたが期待通りでした。ただ、ネタバレになってしまいますが、連続レイプ殺人犯の山田が、自身の犯罪隠ぺい工作を、被害者の母親や友人が暴く行動をとることを知ることができたのはなぜか描かれておらず、物語のキモになる部分だけに、ちょっとモヤモヤ感が残りました。
2021年4月4日 日曜日

吉田大八監督作品「騙し絵の牙」を観ました。原作は塩田武士さんの同名小説です。この作品は俳優の大泉洋を主人公としてイメージして書かかれたもので、当然、映画も大泉洋さんが主演でした。
吉田監督といえば2014年公開の「紙の月」の横領を繰り返す女性銀行員の心理描写がとても印象に残っていて、ミステリーでありながら人の深淵を描く塩田さんの作品を映像化するには、うってつけの監督さんではないかと期待していました。
物語の舞台は、いまやデジタルコンテンツに押されて厳しい状況におかれている出版業界。主人公の速水は老舗出版社「薫風社」に中途入社して雑誌「トリニティ」の編集長に就きますが、社内は次期社長の椅子をめぐって権力争いの真っただ中で、「トリニティ」は廃刊のピンチにおちいってしまいます。
派閥争いに巻き込まれた速水は、専務の東松から無理難題を押し付けられますが、ヘラヘラと人当たりの良い顔の裏側で「次なる一手」を派手に仕掛けてチャンスをつかもうと奮闘します。「そうきたかっ」というエンディングに向ってリズミカルに進むストーリー展開は爽快感さえ感じました。しかも本作はエンターティメントにとどまらず、文化とは何かという難度の高いことを何気なく観客に提示していたと思います。
今は、書店に行かなくても、ネットで簡単に自宅に欲しい本が届く時代になりましたが、それでも本や雑誌を扱う街の書店の存在は私たちに心のゆとりをもたらし、必要不可欠なものだと思います。Amazonに代表されるように効率化を優先させ、大きな利益を上げる手法が世の中を席巻する中で、人の温もりが残ったものを如何にして残していけばいいのか。出版業界だけにとどまらない普遍的なテーマが内包された作品でした。
吉田監督といえば2014年公開の「紙の月」の横領を繰り返す女性銀行員の心理描写がとても印象に残っていて、ミステリーでありながら人の深淵を描く塩田さんの作品を映像化するには、うってつけの監督さんではないかと期待していました。
物語の舞台は、いまやデジタルコンテンツに押されて厳しい状況におかれている出版業界。主人公の速水は老舗出版社「薫風社」に中途入社して雑誌「トリニティ」の編集長に就きますが、社内は次期社長の椅子をめぐって権力争いの真っただ中で、「トリニティ」は廃刊のピンチにおちいってしまいます。
派閥争いに巻き込まれた速水は、専務の東松から無理難題を押し付けられますが、ヘラヘラと人当たりの良い顔の裏側で「次なる一手」を派手に仕掛けてチャンスをつかもうと奮闘します。「そうきたかっ」というエンディングに向ってリズミカルに進むストーリー展開は爽快感さえ感じました。しかも本作はエンターティメントにとどまらず、文化とは何かという難度の高いことを何気なく観客に提示していたと思います。
今は、書店に行かなくても、ネットで簡単に自宅に欲しい本が届く時代になりましたが、それでも本や雑誌を扱う街の書店の存在は私たちに心のゆとりをもたらし、必要不可欠なものだと思います。Amazonに代表されるように効率化を優先させ、大きな利益を上げる手法が世の中を席巻する中で、人の温もりが残ったものを如何にして残していけばいいのか。出版業界だけにとどまらない普遍的なテーマが内包された作品でした。
2021年4月23日 金曜日

養老孟司さんと伊集院光さんの対談本「世間とズレちゃうのはしょうがない」を読みました。
伊集院さんは、見方や立ち位置を変えることで、一見つまらないことでも面白くするラジオパーソナリティとしてのトークが絶妙で「深夜の馬鹿力」という番組をよく聞いています。養老さんは、科学者でありながら仏教的な世界の捉え方をするところが好きで著書はほとんど読んでいます。つまり、私にとっては両者とも興味をひかれる人であるわけですが、「世間とズレる」ということは「生きづらさを生きる」という、現代社会で少なくない人が抱える問題とリンクするところもあるのではないかと思い、この二人の対談に「生きづらさ」をやわらげるヒントがあるかも知れないと思いながらページをめくりました。
話題は登校拒否、戦争、論文、お笑い、AIなど多岐にわたりましたが、まず、現実を切り取る用語として「内」と「外」という概念を持ち出すところから対談はスタートしました。生きている人と死んでいる人、都市と自然、それらが世間の「内」と「外」に対応するというわけです。
見た目が大きくて、子どものころから同級生との違いをひしひしと感じ、世間の「内」からはじき出されることを恐れたという伊集院さんは、不登校になった理由や落語の道に進んだわけを明かしつつ、人間はそもそも群れの中で生きる動物であって、他人に優しくなるほうが得ということになるんじゃないかなと語ります。対して「自分ははじめから世間から外れていた」と語る養老さんは、「都市においては、意識で扱えないものは排除されます」という都市論、世間論を展開。さらに、たまには世間から外れて世の中をながめてもいいんじゃないかと提案します。このあたりは養老さんの「脳推論」を読んでもらうと理解が深まると思うのですが、高度なロジックをかみ砕いて平場で語る伊集院さんの技量はやはりすごいと感じました。
世間とズレていると、不安になります。その不安を知られたくないから、やみくもに周囲と同調し、変化に動じないふりをし「わかりません」という言葉がどんどん言い出しにくくなります。そして、デジタル化に代表されるように何かと便利になればなるほど、その人間がどういう人間なのかが、端に追いやられて「生きづらさ」につながっていると思えます。
そういう世間の内にいて辛かったら、養老さんは「自然に逃げ込め」と言いますが「ああすれば、こうなる」という意識世界の外に出れば、息をするのが楽になるだけでなく、世の中の真実というものが分かるのかも知れません。
伊集院さんは、見方や立ち位置を変えることで、一見つまらないことでも面白くするラジオパーソナリティとしてのトークが絶妙で「深夜の馬鹿力」という番組をよく聞いています。養老さんは、科学者でありながら仏教的な世界の捉え方をするところが好きで著書はほとんど読んでいます。つまり、私にとっては両者とも興味をひかれる人であるわけですが、「世間とズレる」ということは「生きづらさを生きる」という、現代社会で少なくない人が抱える問題とリンクするところもあるのではないかと思い、この二人の対談に「生きづらさ」をやわらげるヒントがあるかも知れないと思いながらページをめくりました。
話題は登校拒否、戦争、論文、お笑い、AIなど多岐にわたりましたが、まず、現実を切り取る用語として「内」と「外」という概念を持ち出すところから対談はスタートしました。生きている人と死んでいる人、都市と自然、それらが世間の「内」と「外」に対応するというわけです。
見た目が大きくて、子どものころから同級生との違いをひしひしと感じ、世間の「内」からはじき出されることを恐れたという伊集院さんは、不登校になった理由や落語の道に進んだわけを明かしつつ、人間はそもそも群れの中で生きる動物であって、他人に優しくなるほうが得ということになるんじゃないかなと語ります。対して「自分ははじめから世間から外れていた」と語る養老さんは、「都市においては、意識で扱えないものは排除されます」という都市論、世間論を展開。さらに、たまには世間から外れて世の中をながめてもいいんじゃないかと提案します。このあたりは養老さんの「脳推論」を読んでもらうと理解が深まると思うのですが、高度なロジックをかみ砕いて平場で語る伊集院さんの技量はやはりすごいと感じました。
世間とズレていると、不安になります。その不安を知られたくないから、やみくもに周囲と同調し、変化に動じないふりをし「わかりません」という言葉がどんどん言い出しにくくなります。そして、デジタル化に代表されるように何かと便利になればなるほど、その人間がどういう人間なのかが、端に追いやられて「生きづらさ」につながっていると思えます。
そういう世間の内にいて辛かったら、養老さんは「自然に逃げ込め」と言いますが「ああすれば、こうなる」という意識世界の外に出れば、息をするのが楽になるだけでなく、世の中の真実というものが分かるのかも知れません。
2021年5月19日 水曜日
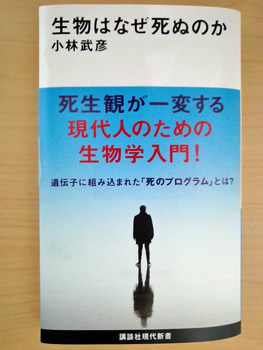
宇宙誕生が138億年前、地球誕生が46億年前、そして生命誕生が38億年前。私たちは地球で生まれ進化し、今の姿になったと教わりました。しかし、先端科学の知見によれば生命の基となるタンパクの合成が自然に起こる確率は10の4万乗分の1で、それは25メートルプールに時計をバラバラにして投げ込んで、水流だけで元通りに組み立てる確率と同じくらいだそうです。
2012年に公開されたリドリースコット監督作品「プロメテウス」では、地球における生命の創造主は地球外生命体であることが判明します。しかし、創造主は生命を消滅させるべく計画していたことも分かり、それは何故なのかという疑問符で物語は終わります。この物語には多くのエゴを持った人間が登場し、これに対し創造主という地球外生命体はある意味罰を与えるものとして描かれているように思えました。
さて、生命誕生の謎はロマンであるにせよ、多くの生命が誕生と死を繰り返して進化してきたことは疑いようがなく、そこにはどんな意味があるのか、これまでも様々な分野の人たちが考えてきました。今回紹介する小林武彦さんの著書「生物はなぜ死ぬのか」も、そんな生命の謎を専門的な知識を駆使して解き明かしてみせてくれる一冊です。
小林さんは生命の連続性を支えるゲノムの再生(若返り)機構を解き明かす研究に長年取り組んでおり、本書でも生物はなぜ老いて死ぬのかという問いに進化論で答えています。
印象に残ったのは、生物が自己を複製するもっとも基本となるRNAの発生から、生物と無生物の違いを解説する中で、コロナウィルスについての解説があり、mRNAはリボゾームで翻訳作業が終了した後は、細胞内プロセスによってすぐに分解されてしまうこと、細胞内ではRNAはDNAに逆転写できないためmRNAワクチンがDNAに組み込まれることはないこと、つまり、mRNAワクチンの長期的なリスクについても知ることができたことです。また、老化や死を克服できるのかという問題で、カロリー制限や抗酸化物質の効果を検証する一方、老化細胞を除去する実験の紹介は興味深く、生命の回数券といわれるテロメア(染色体の末端にあるDNA)を修復したり、そのほかいろいろな老化要因を治療すれば、不老不死も可能になるとはSF映画の世界のようです。しかし、考えるべきは、なぜ老化や死を生命進化(自然選択)は許すのかという問題ではないかと思います。これを考えていくと仏教でいう空の概念と重なるところがあるのではないかと感じました。
2012年に公開されたリドリースコット監督作品「プロメテウス」では、地球における生命の創造主は地球外生命体であることが判明します。しかし、創造主は生命を消滅させるべく計画していたことも分かり、それは何故なのかという疑問符で物語は終わります。この物語には多くのエゴを持った人間が登場し、これに対し創造主という地球外生命体はある意味罰を与えるものとして描かれているように思えました。
さて、生命誕生の謎はロマンであるにせよ、多くの生命が誕生と死を繰り返して進化してきたことは疑いようがなく、そこにはどんな意味があるのか、これまでも様々な分野の人たちが考えてきました。今回紹介する小林武彦さんの著書「生物はなぜ死ぬのか」も、そんな生命の謎を専門的な知識を駆使して解き明かしてみせてくれる一冊です。
小林さんは生命の連続性を支えるゲノムの再生(若返り)機構を解き明かす研究に長年取り組んでおり、本書でも生物はなぜ老いて死ぬのかという問いに進化論で答えています。
印象に残ったのは、生物が自己を複製するもっとも基本となるRNAの発生から、生物と無生物の違いを解説する中で、コロナウィルスについての解説があり、mRNAはリボゾームで翻訳作業が終了した後は、細胞内プロセスによってすぐに分解されてしまうこと、細胞内ではRNAはDNAに逆転写できないためmRNAワクチンがDNAに組み込まれることはないこと、つまり、mRNAワクチンの長期的なリスクについても知ることができたことです。また、老化や死を克服できるのかという問題で、カロリー制限や抗酸化物質の効果を検証する一方、老化細胞を除去する実験の紹介は興味深く、生命の回数券といわれるテロメア(染色体の末端にあるDNA)を修復したり、そのほかいろいろな老化要因を治療すれば、不老不死も可能になるとはSF映画の世界のようです。しかし、考えるべきは、なぜ老化や死を生命進化(自然選択)は許すのかという問題ではないかと思います。これを考えていくと仏教でいう空の概念と重なるところがあるのではないかと感じました。
2021年5月29日 土曜日
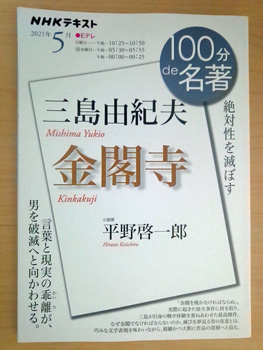
初めて三島由紀夫の作品に触れたのは1975年公開の映画「潮騒」でした。瀬戸内に浮かぶ小さな島が舞台の、どこまでも純粋で美しい恋物語は、田舎の中学生にもいずれは自分にもこんな眩しい瞬間が訪れるかも知れないと、ひそかな希望を抱かせました。
それが、後に読んだ「仮面の告白」「金閣寺」では主人公の暗い内面がひたすら描かれており、その頃自分が抱えていた世の中との葛藤と通じる部分もあって、教師は理解してくれなくても、三島という人は分かってくれるかも知れないと思ったものです。
Eテレ5月のバラエティ番組「100分de名著」は三島由紀夫「金閣寺」でした。1950年7月に実際に起こった「金閣寺放火事件」の外枠だけを使って三島の内面世界を描いた、三島の作品の中では私が一番好きな作品です。
吃音という障害ゆえに社会とうまく付き合っていけない溝口は、絶対的な美の象徴である金閣寺に憧憬を募らせることで、自らの劣等感をいやしています。
やがて溝口は金閣寺の徒弟となり、戦争の業火に金閣寺と共に滅んでいくことを夢見るようになります。しかし、日本は敗戦し、溝口と金閣寺の関係性は決定的に変わってしまいます。戦時中は「滅びゆくもの」として自分と同じ側にあったと思われた金閣寺は、自分からかけはなれた「呪わしい永遠」と化したからです。師である住職との関係、友人たちからの影響の中で溝口は金閣寺を憎むようになり、「金閣寺を焼かなければならぬ」と決意するに至ります。
中学生で読んだ時は、溝口の友人である柏木の「認識を変えればいい」という言葉が胸に刺さって、たしかに世間を変えるよりも自身が変わるほうが楽だと思ったものですが(実際にそうしようと努力しました)、認識よりも行為であると主張する三島が後に「盾の会」を立ち上げて世の中を変えようとしたことは、今、金閣寺を読み返すと戦後、世の中の価値観が全く変わったという経験がない私は共感はできないものの、ある程度は理解できます。
番組解説の小説家、平野啓一郎さんによれば、この作品には「心象の金閣」と「現実の金閣」に引き裂かれながらもその一致を求め続けた主人公の苦悩を通して、現実と理想、虚無と妄信、認識と行為などに引き裂かれて生きざるを得ない私たち人間が直面する問題が刻まれているといいます。そして、三島が苦渋をもって見つめざるを得なかった日本の戦後社会の矛盾や退廃が「金閣寺」という存在に照らし出されるように見えてきます。
この作品は、物事の意義や目的といったものは存在しない、自分自身の存在を含めて全てが無価値なものとして認識する見方と、その上でどうやって生きればいいのかといいう問いであって、日本人にとって「戦後」とは何だったのかを再考させてくれると思います。
それが、後に読んだ「仮面の告白」「金閣寺」では主人公の暗い内面がひたすら描かれており、その頃自分が抱えていた世の中との葛藤と通じる部分もあって、教師は理解してくれなくても、三島という人は分かってくれるかも知れないと思ったものです。
Eテレ5月のバラエティ番組「100分de名著」は三島由紀夫「金閣寺」でした。1950年7月に実際に起こった「金閣寺放火事件」の外枠だけを使って三島の内面世界を描いた、三島の作品の中では私が一番好きな作品です。
吃音という障害ゆえに社会とうまく付き合っていけない溝口は、絶対的な美の象徴である金閣寺に憧憬を募らせることで、自らの劣等感をいやしています。
やがて溝口は金閣寺の徒弟となり、戦争の業火に金閣寺と共に滅んでいくことを夢見るようになります。しかし、日本は敗戦し、溝口と金閣寺の関係性は決定的に変わってしまいます。戦時中は「滅びゆくもの」として自分と同じ側にあったと思われた金閣寺は、自分からかけはなれた「呪わしい永遠」と化したからです。師である住職との関係、友人たちからの影響の中で溝口は金閣寺を憎むようになり、「金閣寺を焼かなければならぬ」と決意するに至ります。
中学生で読んだ時は、溝口の友人である柏木の「認識を変えればいい」という言葉が胸に刺さって、たしかに世間を変えるよりも自身が変わるほうが楽だと思ったものですが(実際にそうしようと努力しました)、認識よりも行為であると主張する三島が後に「盾の会」を立ち上げて世の中を変えようとしたことは、今、金閣寺を読み返すと戦後、世の中の価値観が全く変わったという経験がない私は共感はできないものの、ある程度は理解できます。
番組解説の小説家、平野啓一郎さんによれば、この作品には「心象の金閣」と「現実の金閣」に引き裂かれながらもその一致を求め続けた主人公の苦悩を通して、現実と理想、虚無と妄信、認識と行為などに引き裂かれて生きざるを得ない私たち人間が直面する問題が刻まれているといいます。そして、三島が苦渋をもって見つめざるを得なかった日本の戦後社会の矛盾や退廃が「金閣寺」という存在に照らし出されるように見えてきます。
この作品は、物事の意義や目的といったものは存在しない、自分自身の存在を含めて全てが無価値なものとして認識する見方と、その上でどうやって生きればいいのかといいう問いであって、日本人にとって「戦後」とは何だったのかを再考させてくれると思います。
2021年5月30日 日曜日

成島出(なるしま いずる)監督作品「いのちの停車場」を観ました。原作は南杏子さんの同名小説です。
医師になると同時に大学病院のERで救命救急医として働き、現在はセンター長である白石咲和子は、ERでライセンスがない者(医師国家試験を3回落ち、コネで病院事務職についた野呂)が医療行為を行った責任をとって病院を辞め、老父が一人暮らしをしている石川県金沢市の実家に戻り、小さな診療所に勤務医として就職することになります。
これまでER一筋であった白石が知ってる医療とは違う形での“いのち”との向き合い方に戸惑いを感じる白石でしたが、所長の仙川をはじめ、診療所を支える看護師の星野、白石を慕って金沢にやって来た野呂ら周囲の人々と共に、在宅医療というフィールドで患者やその家族との向き合い方を見いだしていくというストーリーです。
老老介護、肺がんの女流プロ棋士、脊髄損傷のIT社長、小児がんの少女、そして、大腿骨頚部骨折から誤嚥性肺炎、脳梗塞を経て、脳卒中後疼痛にみまわれ「これ以上生きていたくない」と「積極的安楽死」を望む老父。救うことのできない患者たちと白石のかかわりを描く中で、治すことだけが医療の役割なのかという問いかけが本作のテーマであったと思うのですが、ひとりの患者に物語を絞って掘り下げたほうがよかったのではないかと感じました。物語の展開としての人間関係も浅く感じて(特に肺がんの女流プロ棋士)本作のホームページでは社会派ヒューマンドラマとなっていますが、医療ファンタジードラマといったところで、役者は良かったのに脚本が悪すぎて総合評価としてはB級作品だと思います。
医師になると同時に大学病院のERで救命救急医として働き、現在はセンター長である白石咲和子は、ERでライセンスがない者(医師国家試験を3回落ち、コネで病院事務職についた野呂)が医療行為を行った責任をとって病院を辞め、老父が一人暮らしをしている石川県金沢市の実家に戻り、小さな診療所に勤務医として就職することになります。
これまでER一筋であった白石が知ってる医療とは違う形での“いのち”との向き合い方に戸惑いを感じる白石でしたが、所長の仙川をはじめ、診療所を支える看護師の星野、白石を慕って金沢にやって来た野呂ら周囲の人々と共に、在宅医療というフィールドで患者やその家族との向き合い方を見いだしていくというストーリーです。
老老介護、肺がんの女流プロ棋士、脊髄損傷のIT社長、小児がんの少女、そして、大腿骨頚部骨折から誤嚥性肺炎、脳梗塞を経て、脳卒中後疼痛にみまわれ「これ以上生きていたくない」と「積極的安楽死」を望む老父。救うことのできない患者たちと白石のかかわりを描く中で、治すことだけが医療の役割なのかという問いかけが本作のテーマであったと思うのですが、ひとりの患者に物語を絞って掘り下げたほうがよかったのではないかと感じました。物語の展開としての人間関係も浅く感じて(特に肺がんの女流プロ棋士)本作のホームページでは社会派ヒューマンドラマとなっていますが、医療ファンタジードラマといったところで、役者は良かったのに脚本が悪すぎて総合評価としてはB級作品だと思います。
2021年6月12日 土曜日
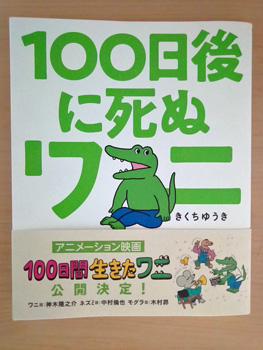
「100日後に死ぬワニ」。この作品は、漫画家きくちゆうきさんの4コマ漫画で、コマの枠外に「死まであと○日」と明示された主人公ワニくんの100日間を、4コマを1日としたカウントダウン形式で描いた作品で、2019年12月から作者のTwitterで公開され、2020年4月に書籍化されました。ネット上で随分話題になり、私も更新を楽しみにしていました。
この作品最大の特徴は、タイトル通り「主人公が100日後に死ぬ」ことがわかっていることです。あらかじめ結末がわかっている物語は面白くないはずなのですが、このマンガの場合はそうではありませんでした。
初投稿の回では、ワニくんがテレビを見ながら笑っている様子が描かれています。一見すると、ほのぼのとして微笑ましい場面ですが、その4コマの下には“死まであと99日”と書かれています。読者は毎回、何気ないワニの日常の4コマを読んだ後に、欄外の死ぬまでのカウントダウンを目にすることで、日常から急に「死」を意識させられます。ワニくんたちの日常が生き生きと描かれれば描かれるほど、いつもの日常であればあるほど、100日後に訪れる「死」が鮮明になってきます。いわば、「生」と「死」のコントラストがとても強いのです。
いろいろな作品で「死」というテーマが扱われています。そしてそのほとんどが、「死」をドラマチックに演出したり、美談にしたり、衝撃的なものにしてしまう傾向が少なくありませんが、「100日後に死ぬワニ」は、ほとんど「死」を感じさせるエピソードは登場しません。最終回ですらワニくんの死ぬシーンは描かれていません。絵のタッチもストーリーも「死」とは真逆であるからこそ「死」が印象的になるのだと思います。
4コマ漫画で泣いたのは初めてですが、生きていること、誰かのことを思うことの尊さを感じました。クリスチャンでホスピス医の細井順先生は、この作品をどう読むか、ぜひお聞きしたいものです。
この作品最大の特徴は、タイトル通り「主人公が100日後に死ぬ」ことがわかっていることです。あらかじめ結末がわかっている物語は面白くないはずなのですが、このマンガの場合はそうではありませんでした。
初投稿の回では、ワニくんがテレビを見ながら笑っている様子が描かれています。一見すると、ほのぼのとして微笑ましい場面ですが、その4コマの下には“死まであと99日”と書かれています。読者は毎回、何気ないワニの日常の4コマを読んだ後に、欄外の死ぬまでのカウントダウンを目にすることで、日常から急に「死」を意識させられます。ワニくんたちの日常が生き生きと描かれれば描かれるほど、いつもの日常であればあるほど、100日後に訪れる「死」が鮮明になってきます。いわば、「生」と「死」のコントラストがとても強いのです。
いろいろな作品で「死」というテーマが扱われています。そしてそのほとんどが、「死」をドラマチックに演出したり、美談にしたり、衝撃的なものにしてしまう傾向が少なくありませんが、「100日後に死ぬワニ」は、ほとんど「死」を感じさせるエピソードは登場しません。最終回ですらワニくんの死ぬシーンは描かれていません。絵のタッチもストーリーも「死」とは真逆であるからこそ「死」が印象的になるのだと思います。
4コマ漫画で泣いたのは初めてですが、生きていること、誰かのことを思うことの尊さを感じました。クリスチャンでホスピス医の細井順先生は、この作品をどう読むか、ぜひお聞きしたいものです。
2021年6月24日 木曜日

2021年6月のEテレ、読書バラエティ番組「100分de名著」は、映画化もされたSFディストピアの傑作、レイブラッドベリの「華氏451度」でした。
SFというジャンルでは「スターウォーズ」よりも「インターステラー」「エクスマキナ」などが好みなので、今回の「華氏451度」は楽しみにしていました。(スターウォーズはどう観てもファンタジーにしか思えません)
現在、日本では温度を表すのに摂氏という単位を使っていますが、アメリカやイギリスなどでは華氏が使われることも多いようです。摂氏(セルシウス)も、華氏(ファーレンハイト)も、それぞれを考案した科学者の名前が由来となっており、摂氏0度は華氏32度、摂氏100度は華氏212度になります。なので華氏451度は摂氏に換算すると(451-32)/1.8で約233度、紙が自然発火する温度です。
主人公のガイモンターグは本を燃やす「ファイヤマン」という仕事に従事しています。彼の暮らす近未来では、本が有害な情報を市民にもたらすものとされ、読むことはもちろん所持も禁止。本が発見されると直ちにファイアマンが出動し全ての本を焼却、所有者も逮捕されます。
こんな世界で人々の思考を支配しているのは、視聴者参加型のテレビとラジオ。彼の妻も、まるで中毒患者のようにその快楽におぼれていますが、自分では気付いていません。
最初は規律を守る隊員だったモンターグでしたが、自由な思考をする女性クラリスや、本と共に焼死することを選ぶ老女らとの出会いによって少しずつファイアマンという仕事に疑問を持ち始め、やがて密かに本を読み始めるモンターグ。その彼が選択した未来とは、そして、世界はどこへ向かうのか。物語は衝撃の結末を迎えます。
本を焼却し去り、人間の思考力を奪う反知性主義と全体主義社会の恐怖。効率化の果てに人々が自発的に思考能力を放棄してしまう皮肉や、記憶や記録をないがしろにする社会の貧しさ。ここに描かれている人々の姿は、ネトゲやSNSに踊らされ、自分で思考し何かを問い続けることを忘れてしまった私たちそのものに思えます。この作品が書かれたのは70年以上前ですが、全体主義的な風潮がじわじわと世界を侵食する現代に通じているようで、まるで予言書のように思えてしまいます。(だとしたら恐ろしいです。)
思考することで得られる真の自由を失いたくはないものですが、今、もっともこれを強く感じているのは香港市民ではないでしょうか。リンゴ日報の廃刊と立花隆さんの訃報が悲しい梅雨の朝でした。
SFというジャンルでは「スターウォーズ」よりも「インターステラー」「エクスマキナ」などが好みなので、今回の「華氏451度」は楽しみにしていました。(スターウォーズはどう観てもファンタジーにしか思えません)
現在、日本では温度を表すのに摂氏という単位を使っていますが、アメリカやイギリスなどでは華氏が使われることも多いようです。摂氏(セルシウス)も、華氏(ファーレンハイト)も、それぞれを考案した科学者の名前が由来となっており、摂氏0度は華氏32度、摂氏100度は華氏212度になります。なので華氏451度は摂氏に換算すると(451-32)/1.8で約233度、紙が自然発火する温度です。
主人公のガイモンターグは本を燃やす「ファイヤマン」という仕事に従事しています。彼の暮らす近未来では、本が有害な情報を市民にもたらすものとされ、読むことはもちろん所持も禁止。本が発見されると直ちにファイアマンが出動し全ての本を焼却、所有者も逮捕されます。
こんな世界で人々の思考を支配しているのは、視聴者参加型のテレビとラジオ。彼の妻も、まるで中毒患者のようにその快楽におぼれていますが、自分では気付いていません。
最初は規律を守る隊員だったモンターグでしたが、自由な思考をする女性クラリスや、本と共に焼死することを選ぶ老女らとの出会いによって少しずつファイアマンという仕事に疑問を持ち始め、やがて密かに本を読み始めるモンターグ。その彼が選択した未来とは、そして、世界はどこへ向かうのか。物語は衝撃の結末を迎えます。
本を焼却し去り、人間の思考力を奪う反知性主義と全体主義社会の恐怖。効率化の果てに人々が自発的に思考能力を放棄してしまう皮肉や、記憶や記録をないがしろにする社会の貧しさ。ここに描かれている人々の姿は、ネトゲやSNSに踊らされ、自分で思考し何かを問い続けることを忘れてしまった私たちそのものに思えます。この作品が書かれたのは70年以上前ですが、全体主義的な風潮がじわじわと世界を侵食する現代に通じているようで、まるで予言書のように思えてしまいます。(だとしたら恐ろしいです。)
思考することで得られる真の自由を失いたくはないものですが、今、もっともこれを強く感じているのは香港市民ではないでしょうか。リンゴ日報の廃刊と立花隆さんの訃報が悲しい梅雨の朝でした。
2021年6月27日 日曜日

SF作品ではテーマにされることが多い、もし、人類の不老不死が実現したら個人や社会はどうなるのか。中国系アメリカ人作家ケンリュウさんの短編小説を石川慶監督が映画化した「Arc アーク」を観ました。
舞台は近未来。不老不死が実現した世界で、30才の肉体のまま永遠に生きていくことになる女性リナを主人公に、永遠の命を得た人間が見る景色を鮮やかに描いたSF作品です。現在の世界と地続きでつながっていると感じさせてくれる物語の社会的ディティールがしっかりしているところが私好みでした。
物語の前半、不老不死化というのはあくまで一部の人だけが享受できる特権として描かれますが、時間が経過して数十年後になると社会の雰囲気が変わって、多くの人にとって不老不死化が当然になった反面、社会から活気が失われて何となく弛緩した空気感が漂います。そこに「出生率は0.2パーセントを切る一方、自殺率は高止まりしています」というカーラジオの声。ちょっとしたリアリティの演出がすごくよかったです。
全体的な印象としてはテクノロジー自体を善か悪かというジャッジをしない、ありがちなディストピア物語としては描いていないところが新鮮で、映像的には物語の後半、経済的な理由から不老不死の手術を受けられなかった人たちが老後を過ごす施設のシーンで、海辺の町の美しい風景をカラーとモノクロで表現していたのですが、このコントラストが印象的でした。
リナの人生に対する考え方も年齢に応じて微妙に変わっていき30才と90才、136才とで、不老不死に対する彼女の受け止め方が変わっていくところも見どころだと思います。
舞台は近未来。不老不死が実現した世界で、30才の肉体のまま永遠に生きていくことになる女性リナを主人公に、永遠の命を得た人間が見る景色を鮮やかに描いたSF作品です。現在の世界と地続きでつながっていると感じさせてくれる物語の社会的ディティールがしっかりしているところが私好みでした。
物語の前半、不老不死化というのはあくまで一部の人だけが享受できる特権として描かれますが、時間が経過して数十年後になると社会の雰囲気が変わって、多くの人にとって不老不死化が当然になった反面、社会から活気が失われて何となく弛緩した空気感が漂います。そこに「出生率は0.2パーセントを切る一方、自殺率は高止まりしています」というカーラジオの声。ちょっとしたリアリティの演出がすごくよかったです。
全体的な印象としてはテクノロジー自体を善か悪かというジャッジをしない、ありがちなディストピア物語としては描いていないところが新鮮で、映像的には物語の後半、経済的な理由から不老不死の手術を受けられなかった人たちが老後を過ごす施設のシーンで、海辺の町の美しい風景をカラーとモノクロで表現していたのですが、このコントラストが印象的でした。
リナの人生に対する考え方も年齢に応じて微妙に変わっていき30才と90才、136才とで、不老不死に対する彼女の受け止め方が変わっていくところも見どころだと思います。
